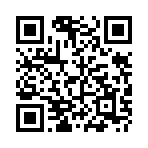2018年07月19日
出張報告 ドクターイエロー
先日、店長たちと一緒に出張に行きました。
その時のお話です。
(出張内容は、経営などに関する、ちょっと固い内容ではありました。)
店長たちとの出張機会も少ないため非常に珍しく、
出張の内容自体も非常に有意義なものでしたが、
その帰り道の東京駅にて人混みが。
皆さんの目線の先に目をやると、黄色い新幹線が停まっていました。
私が知っていた名前「ドクターイエロー」は通称だそうで、
正式名称は「新幹線電気軌道総合試験車」だそうです。
観ると幸せになると一部の方から言われている「ドクターイエロー」。
私は初めて見ることができましたが、
なんとなく幸運になれそうな気持になりました。
出張内容に成果がでるよう、
鉄道の神様が応援してくれているような、そんな気持ちになりました。
2018年05月07日
静岡鋳物「栗田産業」様に伺いました①

先日、静岡の「栗田産業様」という鋳物屋さんに出張に行きました。
(栗田産業様のHPはこちら。)
「鋳物」という言葉に対して、皆様はどのようなイメージがあるでしょうか?
私は、ドロドロに溶かした金属を、流し込む。そんなイメージでした。
そのため「金属の加工」という産業の少ない静岡では、
鋳物屋さんがないのではないか?と思っていました。
実際、静岡では鋳物屋さんが一時的に衰退してしまった時期があるようです。
今回、出張で伺った栗田産業様の創業者である重太郎様は、
東京での修行後、明治23年に静岡で鋳物屋さんを開業されたそうです。
実際に拝見させて頂いた鋳物屋さんの工場内は、
時折火柱があがったり、
ドロドロに溶けた金属を流し込んだりする風景でした。

しかしお話を伺ったところ、
全体の工程から考えると、型作成にかなりの労力が費やされているとのことでした。
(鋳物作成のプロセスやこちら。)
工場見学の後に、
「錫でぐい吞みをつくる」というワークショップにも参加してきました。
このワークショップにて、鋳物が静岡の工芸らしいなと強く感じることができました。
(※ワークショップについては、またブログにて紹介をさせて頂きます。)
「挑戦する鋳物屋」栗田産業様と一緒になって、
お客様に喜んでいただける取り組みができたらいいなと思っています。
2018年04月09日
出張報告(鰹節工房やまじゅう様)
一か月ほど前になりますが、焼津の【鰹節工房】やまじゅう様に見学に行きました。
きっかけは、三保原屋本店で鰹節削りを買われたお客様から
「鰹節はどこに売っているの?」というお声を頂いたのがはじまりです。
呉服町商店街も現在は随分とお店が入れ替わり、
かつて乾物屋さんやお茶屋さんで取り扱っていた鰹節が、
身近なお店では、なかなか手に入らないものになりつつあります。
そもそも鰹節について殆ど何も知らなかったので、
やまじゅう様に機会を頂き、工場を見学させて頂くことになりました。
やまじゅう様は【手火山(てびやま)造り】という手法にこだわりを持って、鰹節をつくられています。
手火山造りとは、カツオを焙乾(ばいかん:燻して乾燥する)する方法です。
強い火力でじっくりと燻して乾かすことで、独特の香りと味を造り出すため、
江戸時代の昔より、この手火山造りが一番と言われてきたそうです。
ただし、手間のかかる工程があるため、現在は日本でも数社しか行われていない手法になっています。
やまじゅう様は、作業工程の全てに人の手と目を入れているため、
現場を見学すると、すごく丁寧な鰹節造りを肌で感じることができます。
たとえば、燻す際の鰹節一本一本の置き方や、
燻し加減が偏らないように様子を見ながら鰹節の位置を変えるなど。
その工程の全てを見た後に鰹節を見て、
鰹節をつくるために数か月の工程が必要だという事実が分かると、
鰹節自体もっともっと高価でもいいのかもしれないと思わざるを得ませんでした。
(今回は都合があって本枯れの鰹節の製造工程は拝見できませんでした)
(こちらの写真は、工房の全体を写したもの。とても雰囲気のある工房でした。)
使われている道具の1つ1つに歴史やこだわりを感じることが出来るのも、
工房ならではの面白みだと感じました。
(たとえば、写真の包丁は、カツオをさばく際に使っているもので、
使い続けて、刃を研ぎ続けた結果、包丁の刃が驚くほど薄くなっています)
いつか、三保原屋本店の1階でも、
やまじゅう様の鰹節を販売して、お客様にも、やまじゅう様にも喜んで頂きたいなと強く感じました。
三保原屋本店のHPはこちら。
※鰹節造りについては、やまじゅう様のHPでも詳しい説明がございます
是非、やまじゅう様のHPもご覧ください。→こちら