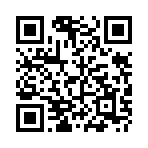2020年11月11日
月兎印の琺瑯シリーズ ~ブラック~

ゲットの愛称で御馴染みの「月兎印」。
生活雑貨を扱う会社が作った印で、
「琺瑯商品」を日本の日常生活に溶け込ませました。
今では琺瑯商品は、老若男女問わず人気のキッチン雑貨。
ガラス質のため、汚れやにおいがつきにくく、雑食の繁殖を防いでくれる他、
保温性・冷却性に優れているので、煮込み料理や漬物などの保存容器としても適している優れものです。
鮮やかな色合いが似合う、琺瑯シリーズは、「黒」もとても美しく見せてくれます。
まるで黒鍵のように、
艶のある上品な風合いの「黒」。
クールで気品あふれる黒の琺瑯。
是非店頭にてご覧下さいませ。
2020年11月10日
信楽焼 塩壷

今の暮らしにちょうどいい3つの特徴を持っています。
①呼吸・調湿する
目が粗く多孔質な信楽の土が、外気と呼吸して湿度を調節。お塩にとって本来の『ちょうどいい』状態をたもってくれています。
②使いやすい
軽くてつまみやすい蓋。キッチンでちょうど良い広口タイプ。
③可愛らしいデザイン
機能面だけでなく、信楽焼ならではの質感や土味。置いてあるだけでもインテリアとして暮らしに馴染み安い、シンプルで可愛らしいデザインです。
目の粗い信楽特有の土が湿度を調節してくれます。
サラサラのお塩はサラサラのまま。海
塩系のしっとりとしたお塩はしっとりとした状態にお塩にとって本来のちょうどいい状態を保ってくれます。
内側は、ガラス質の釉薬をかけていないため吸湿しやすく、塩を付着しにくくしています。
外側は、表面削り仕上げで陶土に近い成分の釉薬を薄く施してあります。
2020年11月09日
繰り返し使いたくなるシリーズ ~しゃもじ~

何度使用しても使い勝手の良さに惹きつけられる商品を紹介します。
極(きわみ) しゃもじ。
この商品は何よりも気持ちよい『シャリ切り』ができます。
最初に三保原屋本店の店長が試して気に入り、その後、お客様の中のモニターさんのテストでも大好評でした。
マーナから販売されている『立つしゃもじ』も、よく売れている商品ですが、
比べると『より、こびりつきにくく』なっている印象です。(写真の2枚目から5枚目にかけて、立つしゃもじとの比較をしております。)
しゃもじの面が少し大きい印象を受けますが、
小ぶりの茶碗でも十分にお使いいただけるサイズ感となっています。
しゃもじを使わないときは、裏面が机につかないよう、少し高さをつけることができる足がついております。
店長も、スタッフもお気に入りの商品です。
是非お試しください!
2020年11月08日
ワラ釜敷き(Lサイズ)

冬が近づくにつれ、恋しくなるのが温かい料理。
特に大鍋で作るシチューやおでん、鍋料理はこれから頻繁に登場しそうです。
写真の商品は、ワラ釜敷き。
見た目も温かみがあり鍋料理に合うデザイン。
見ていてほっこりします。
新潟県佐渡ヶ島でひとつずつ丁寧に作らており、
約2cmの厚みにしっかりと編まれているので、テーブルに熱が伝わりにくく安心です。
素朴ながらも、どこかかわいらしさを感じ、使うたび愛着のわく一品。
今年のお鍋のお供にいかがでしょうか。
こちらの商品は、通販サイトBASEでもご購入頂けます。
2020年11月07日
スプレーポンプ(お醤油スプレー)

塩分のとりすぎは、高血圧をはじめ、様々な生活習慣病と関わりがあり、
醤油スプレーは、良く健康番組でも話題にはあがる商品です。
塩分の摂取目標値を、日本と世界で比べてみると、
(日本)厚生労働省:1日あたり成人男性が9g未満、女性が7.5g未満
(世界)WHO(世界保健機構):1日あたり5g
(米国)心疾患の予防ガイドライン:1日あたり3.8g~6.0g
となっています。
ちなみにですが、コンビニエンスストアのおにぎり1つに含まれる塩分(塩分相当量)は、
多いものは1.5gほど。少なめなものは0.9gほど、となっているようです。
日本人が大好きな、お寿司、海鮮丼などは、酢飯自体にも多くの塩分が含まれており、
更にお醤油をつかってしまうと、どうしても塩分を取りがちになってしまう傾向があるようです。
減塩ブームとともに、その必要性が明らかになってきたのが、お醤油をスプレーで出せるような容器です。
醤油をワンプッシュできるスプレー型の容器は、
一度押すと、お醤油を0.1cc、広い範囲にかけることができます。
少量のお醤油を使いたい方にはとても便利な商品。
本体はガラスなので、酢や酒も使うことができます。(百円ショップで販売されているものは殆どが本体がプラスチックです。)
2020年11月06日
野田琺瑯 ホワイトシリーズ

昨日紹介した琺瑯のポット。
当店では、ホワイトシリーズも人気です。
もちろん製造元はホワイトシリーズで人気の野田琺瑯です。
日本で琺瑯を作れる会社さんが少なくなったなかでも根強い人気がある野田琺瑯。
琺瑯は見た目もかわいいですが、長く使われている理由はそれ以外にもあります。
琺瑯は、金属の表面にガラス質の釉薬を焼き付けた素材です。
他の素材と比較していくと、琺瑯の長所は、
●ガラスは匂いや汚れが落としやすく、細菌の発生を防ぎます
●酸やアルカリなどに強く、化学変化しない
●見た目も美しい
●直火で使うこともできる(レンジ不可)
といった点にあります。
一方で琺瑯のデメリットは、
●表面がガラスなので強い衝撃が加わると割れることがある
●電子レンジが使えない(内部に金属が含まれるため)
●琺瑯がかかっていない箇所や、琺瑯が剥がれた箇所が錆びる可能性がある
(錆は無害なので、お使いいただいても構いません。)
という点が主だと思います。
そのため、電子レンジでのご利用を考えている方にはおススメできません。
ご用途にあわせて、お好きな素材をお使い頂くのが良いかと思います。
適している用途は、お味噌/梅干し/ぬか漬け/ジャムなどです。
また、三保原屋本店の店頭では、ホワイトシリーズのシール蓋のみの販売もしております。
2020年11月05日
月兎印スリムポット

寒くなってくると、より可愛さが際立つ月兎印スリムポット。
兎のマークが象徴的なロングセラー商品。
製造元はホワイトシリーズで人気の野田琺瑯です。
琺瑯の表面はガラス質。内側は金属(鉄)です。
金属のサビやすさを、ガラスでコーティングすることで、
美しく・さびにくい仕上がりになっています。
なんでも工場で自動化が進んでいる印象の現代ですが、
琺瑯は成型された鉄に、ガラス質の釉薬を一つずつ手作業でかけてつくられています。
非常に手間がかかっているためか、なんとなく温かみや愛らしさが伝わる商品です。
2020年11月04日
美しい台所を演出するキッチン雑貨たち

台所は、毎日利用する日常に欠かせない空間。
だからこそ、綺麗に美しく保っていたいものです。
例えば、料理研究家の有元葉子さんの台所は、整然としていてお洒落。
まさにお手本となるような場所です。
その有元さんが発案した「ラバーゼ」。
シンプルでありながら、とても美しく・実用性も兼ね備えた上質な調理器具です。
また、安心の日本製で、生産は新潟県燕三条地区。
燕三条は、世界有数の金属加工の集積地です。
そこで確かな技術を持つ職人により、一つ一つ丁寧に作られました。
清潔感のある空間作りに必要な要素として、
キッチン雑貨の選び方は大切です。
ご自身の理想的な空間作りに、雑貨から見直してみませんか。
ラバーゼは、
当店1Fキッチン雑貨のコーナーにてご紹介しております。
是非ご覧下さいませ。
2020年11月03日
キッチン便利商品 ~アップルカッター~
三保原屋本店の面白キッチン雑貨の紹介です。
今回のブログ写真、
一体どんなキッチン雑貨か、ご存知でしょうか??
直径は外寸で12cm程度、高さは2.5cm程度です。
ハンドルはABS樹脂で、内側はステンレスでできています。
こちらの商品は、
「アップルカッター」という、リンゴを切る道具です。
使い方は、以下の通りです。
①平らな場所にりんごを置く。
②アップルカッターがりんごの真上にくるようにセットする。
③ハンドル部に両手を添えて、力を入れながら下方に押し切る。
リンゴを食べたいけれど、
準備の手間がめんどくさい方など、非常に重宝するのではないでしょうか。
なお、こちらの商品は、
大きすぎるリンゴ(直径8.5cm以上のもの)、
形がいびつなリンゴにはお使い頂くことが出来ませんので、
あらかじめご了承ください。
2020年11月02日
伝統的な遊牧民絨毯

遊牧民の絨毯として人気の高い「ギャッベ」。
ギャッベとは、イラン南西部、ザクロス山麓で遊牧生活を送るカシュガイ族が
作っている手織り絨毯です。
最初から最後まで、全工程をハンドメイドで仕上げており、
素材はウール100%。
更に染めも草木染と天然の成分で染めております。
そのため、1点1点風合いが異なるのが魅力の一つ。
また、柄や模様は一目みても、独特な雰囲気が漂います。
それには、カシュガイ族ならではの文化や感性が反映されており、
より味わい深さを増しているようです。
そして、「ギャッベ」には、「オールド・ギャッベ」という種類もございます。
「オールド・ギャッベ」とは、織られてから20~30年間倉庫で保管されていたものを言います。
デザインや色彩感覚は、「ギャッベ」とは異なり、
「自由奔放な躍動感」が表現されているのが特徴です。
前述と同様に、当時のカシュガイ族の文化や生活スタイルなどを彷彿とさせ、
歴史的価値すら感じさせます。
知れば知るほど、興味深い「遊牧民の絨毯」の世界。
今記載したのは、ほんの一握りです。
当店には、他にも様々な種類の遊牧民絨毯がございます。
是非、店頭にてご覧下さいませ。
絨毯は、3F絨毯コーナーにてご紹介しております。
(一部、2Fインテイリアのコーナーにもございます。)