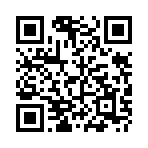2021年07月26日
先日、常滑に行きました
先日、常滑にいきました。
常滑といえば急須!
(まず伺ったのは、磯部商店さん!)
急須ってどのように作られているか??ご存知でしょうか。
私のなかでは、急須は「お皿などに比べて”部品が多い焼き物”。」という感覚。
土鍋や急須は、本体に対して、蓋や持ち手など部品が多くて手間がかかる品物です。
三保原屋本店で扱っている商品は、
どんな商品も、工場内の機械から「製品」としてキレイに出てくるものはありません。
どれも、どこかに手がかかっている、、そしてそれが値段の差になって表れることがあります。
非常に、非常に、非常に、省略して書いたとしても・・・
まず、本体・持ち手・注ぎ口・蓋・持ち手・茶こし、それぞれが別パーツとしてつくられます。
それを組み立てて(必要な部分には穴をくりぬき、パーツごとを繋ぎ合わせ・・)、
焼いて、色をつけていき・・・
と、それぞれの工程すべてが手作業です。
部品ごとを繋ぎ合わせたりする作業などもあり、とにかく大変。
一定以上の品質でモノづくりをしようと思うと、大量生産はどうしてもできず、中量生産といったイメージでしょうか。
(もちろん、作家さんのようにろくろですべて作業をされる方は、少量生産となります)
また、焼き物なので、つくったものが100%製品化されるわけではなく・・
途中で製品に傷ができてしまい、売り物にならないものなどもあります。
それらの作業を全て人手で行います。
どの産地も高齢化が進んでいると聞きました。
ペットボトルのお茶も、急須で淹れたお茶を目指して開発されるようなフレーズを聞きますが、
美味しいお茶はとにかく急須。
是非、三保原屋本店でも急須をご覧になってください。